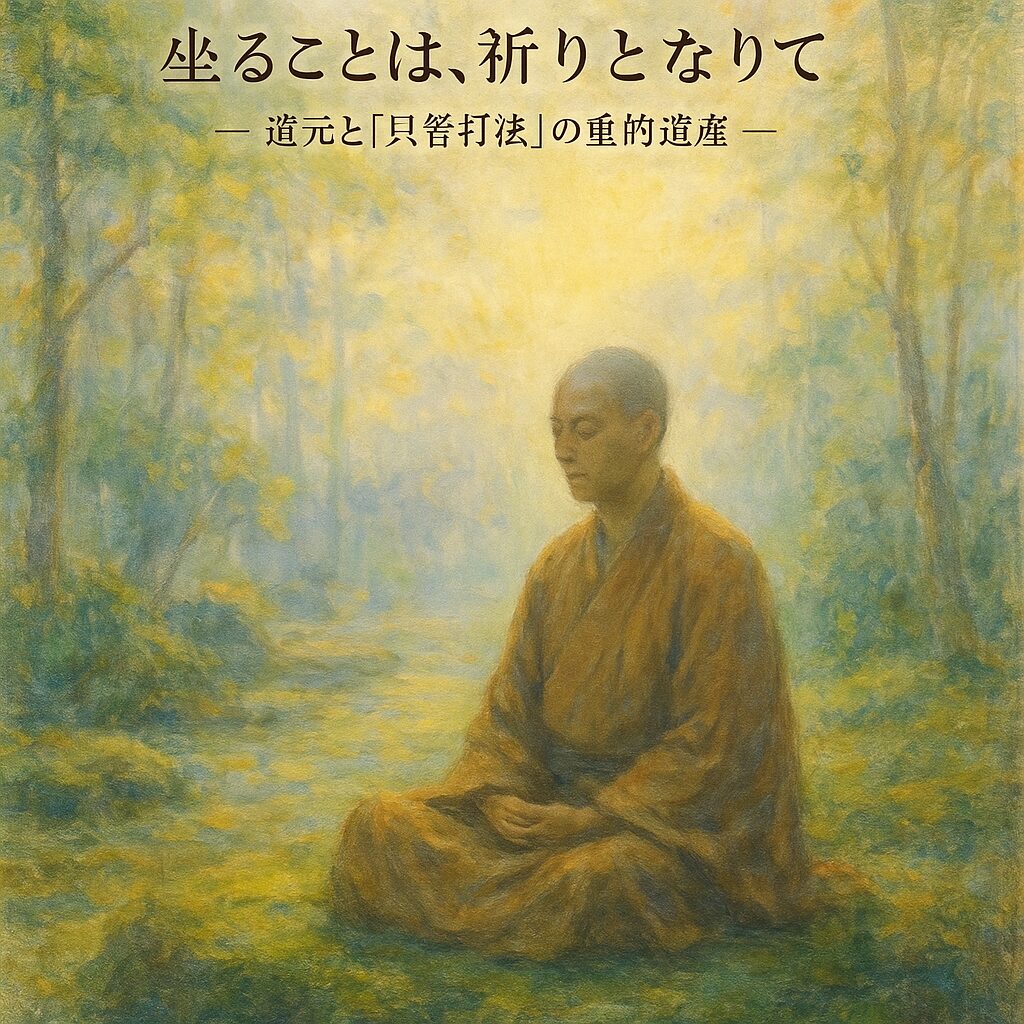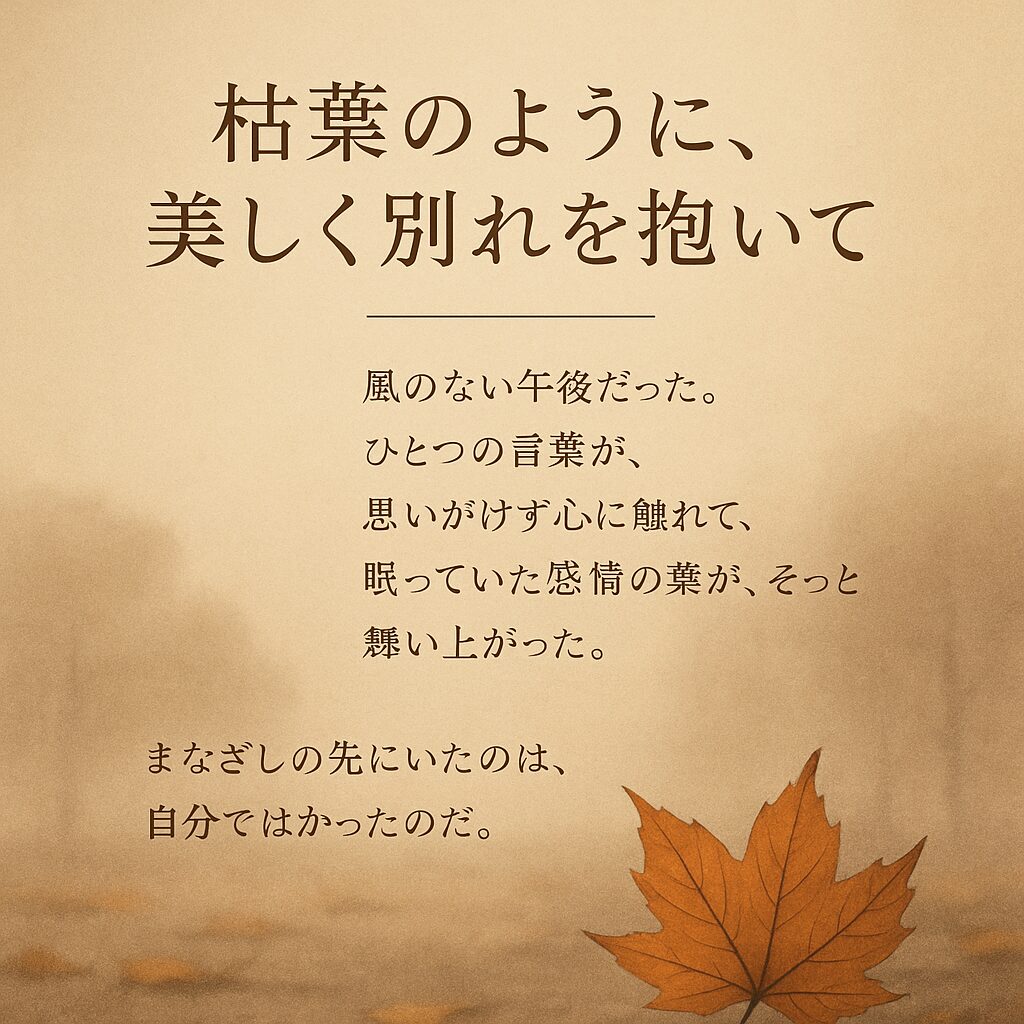風のない午後だった。
静寂は空気に溶け、世界はまるで時を忘れていた。
そんなとき、不意に胸を撫でた一片の言葉。
それは声にさえならなかったけれど、
たしかに私の奥深くで、何かを目覚めさせた。
眠っていた感情の葉が、そっと舞い上がった。
季節のなかで役目を終え、
それでもなお陽に憧れるかのように――。
それは確信ではなく、
ただ、かすかな予感だった。
どこかで名を呼ばれたような気がした。
誰かの心に、一瞬でも触れていたのではないかと。
選ばれたのではないかと――
心が、張り詰めた弓のように微かにしなり、
見えない的を探し続けた。
けれど、その揺れは独りきりの旋律だった。
聴く耳もなく、応える声もないまま、
そっと胸の奥で静かに消えていった。
まなざしの先にいたのは、
私ではなかったのだ。
落ちた葉のように、
ひとつの想いが、音もなく手を離れていく。
劇的な別れではない。
涙もなければ、抱擁もない。
ただ、自然の流れに沿うように、
終わるべきものが、終わっただけだった。
私は、拾わない。
もう戻すことのできない想い。
それでも否定はしない。
その葉はたしかに命を宿し、
一度だけ陽を浴び、風を知り、
誰かに届きたいと震えていたのだから。
それは、美しかった。
空想のなかにだけ還るかたちとなり、
静かに土へと還ってゆく。
それは無意味ではなかった。
芽吹き、揺れ、落ち、還る。
すべてがひとつの輪廻であるなら、
その一瞬に宿った輝きこそが、魂の証だ。
私はかつて、
誰かに触れたいと願った。
愛されたいと、必死で空に向かって手を伸ばした。
届かなくても、笑われても、
その愚直さをいまでは誇りに思っている。
なぜなら――
その愚かさすら、
いまの私を形づくる「美学」のひとつだから。
何もかもを手放してなお、
胸の奥に残るのは、音にならない旋律。
耳をすませば、遠くでかすかに鳴る、
古いシャンソンのような愛の余韻。
過去は消え去ったのではない。
魂のなかで、今も優しく揺れている。
私は、もう追わない。
けれど、何ひとつ失ってはいない。
この沈黙のなかで、
私は私を取り戻している。
そしていつか、
もしまた心が誰かにふれる日がくるのなら――
この哀しみも、希望も、
すべてを抱いて調律された旋律として、
美しく奏でられるように。
私は今日も、
ひとりきりで
静かに、魂の音を合わせている。
それは、孤独という名の静かな祈り。
愛が去ったあとの余白を、
やがて光が満たしてゆくことを、
私の魂は知っている。