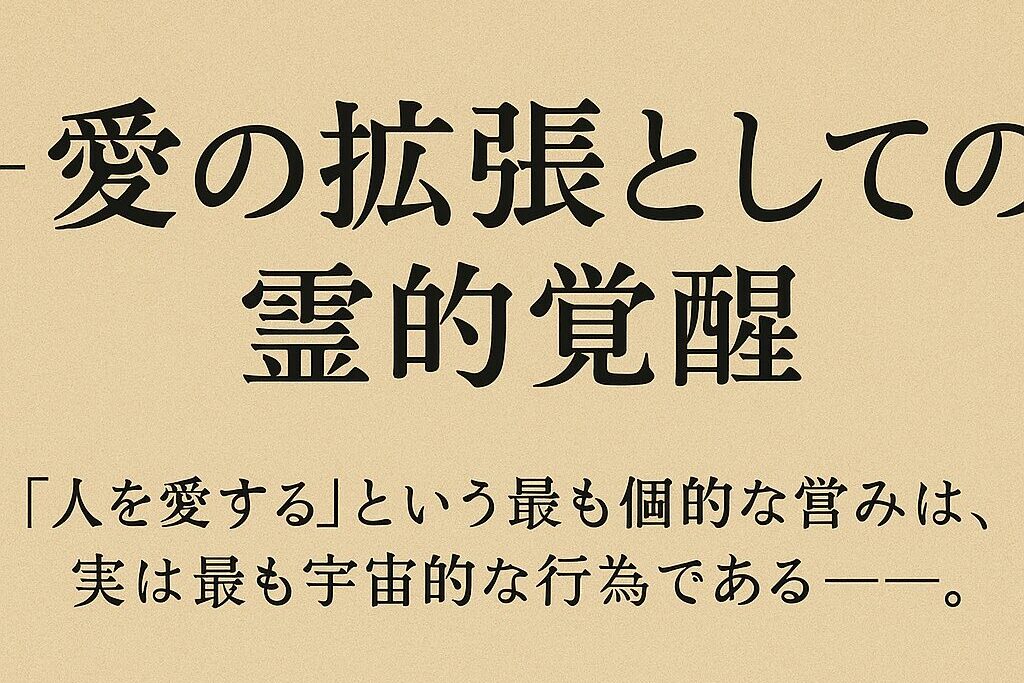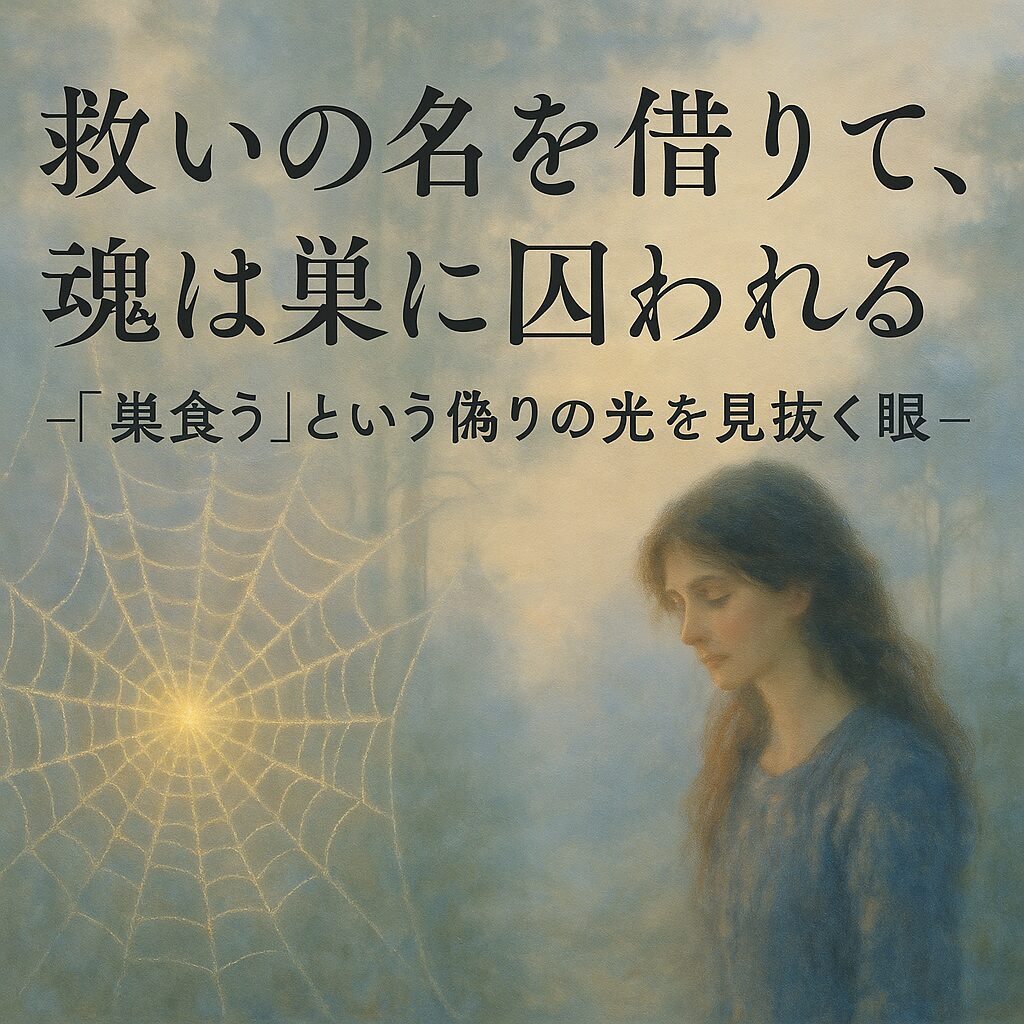-

-
マッカーシズムの亡霊が教える『恐怖の政治学』~歴史は繰り返す。でも、私たちは学べる~
1950年代のアメリカで吹き荒れた「赤狩り」。あの時代の亡霊が、いま再び私たちの社会に忍び寄っています。 2025年9月 ...
-

-
フランス革命が「結果にコミット」できた理由──制度設計の力
I. 序論:革命は理念だけでは完成しない 「自由・平等・友愛」──フランス革命のこのスローガンを知らない人はいないだろう ...
-
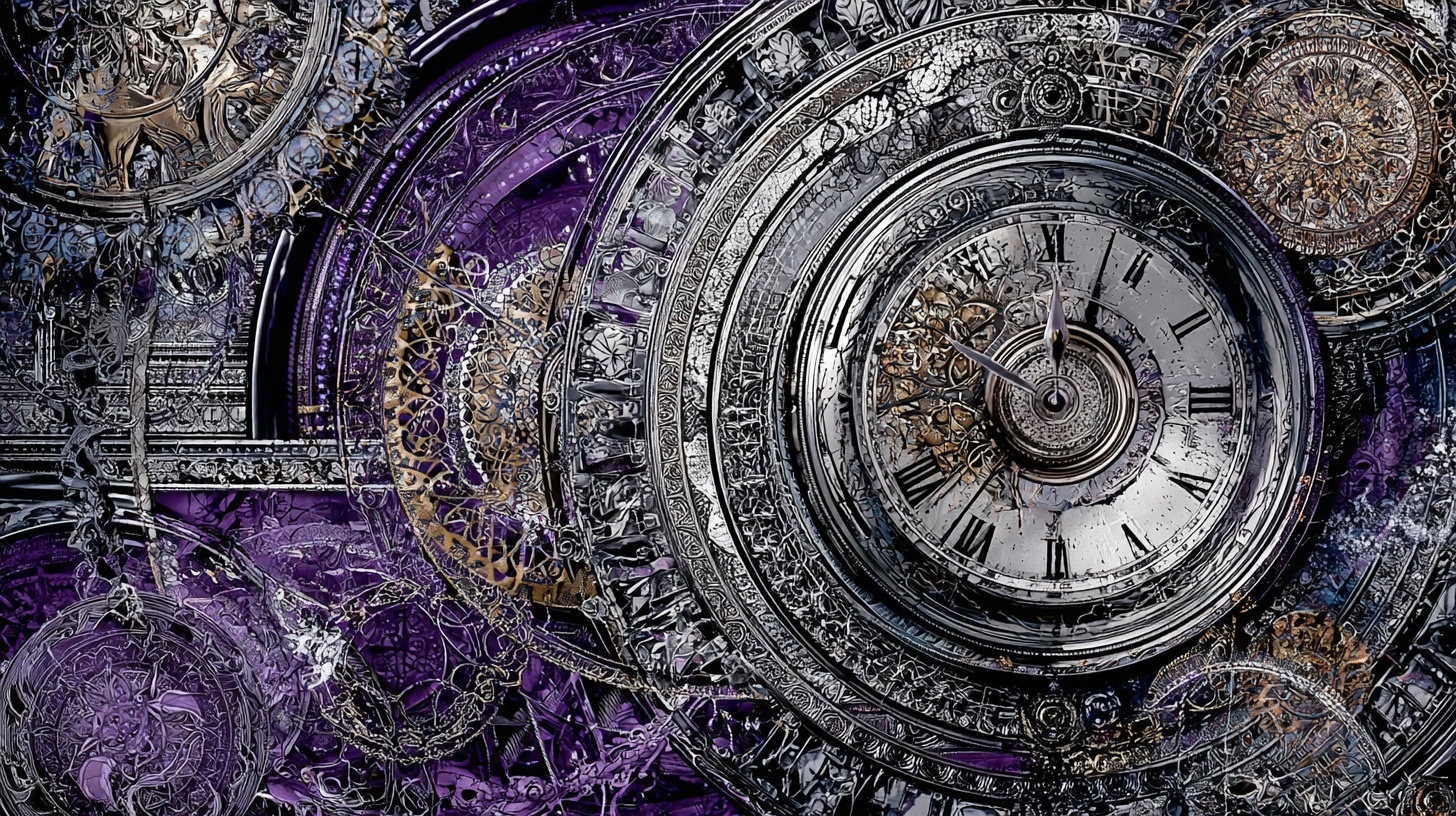
-
思想工学における多時間意識アーキテクチャ:歴史的パターン錬金術と意識進化のための理論的枠組み
著者: 吉祥礼(Ray Kissyou)日付: 2025年9月論文種別: 理論探究・思考実験論文 🔬 理論的研究について ...
-

-
デジタル時代における集合的トラウマの構造分析
ネットワーク型弾圧の理論的枠組み — 思想工学による理論探索論文 著者: Ray Kissyou(吉祥礼) |所属: ...
-

-
現代社会における霊的OS更新理論の構築
―思想工学による理論的探究とシステム変革の仮説的枠組み― 著者: 吉祥礼(Ray Kissyou)発表年: 2025年9 ...
-

-
ネパール暴動に見る小国の霊的主権論——思想工学による21世紀社会設計の五原則
思想工学による社会システム分析:現代社会設計の理論的枠組み ~2025年ネパール社会変動を手がかりとした考察~ Abst ...
-

-
思想工学における文化的認知アーキテクチャ理論:物語OS分析による魂の主権確立システム
著者:Ray Kissyou(吉祥礼) 研究分野:思想工学、文化的認知システム、意識進化理論 要約(Abstract) ...
-

-
文化的物語システムの構造分析:日本の「敗者の美学」とグローバル・ナラティブの進化
序章:文化的認知システムとしての物語OS理論 1.1 問題の所在 『鬼滅の刃』の国際的な受容において観察される文化的反応 ...
-

-
物語OSとしての文化:なぜ日本人は敗者を愛し、アメリカ人はスピードを求めるのか
思想工学における理論的探究論文 要旨 本論文は、文化的な物語の好みを「物語OS(オペレーティングシステム)」という概念で ...
-

-
天皇システムの思想工学的分析:「静かな光」としての社会統合アーキテクチャ
Author: Ray Kissyou (吉祥礼) Date: September 2025 Category: Tho ...
-

-
象徴天皇制の社会学的考察:権威・文化資本・社会統合の理論的分析
Author: Ray Kissyou (吉祥礼) Date: September 2025 Category: Pol ...
-
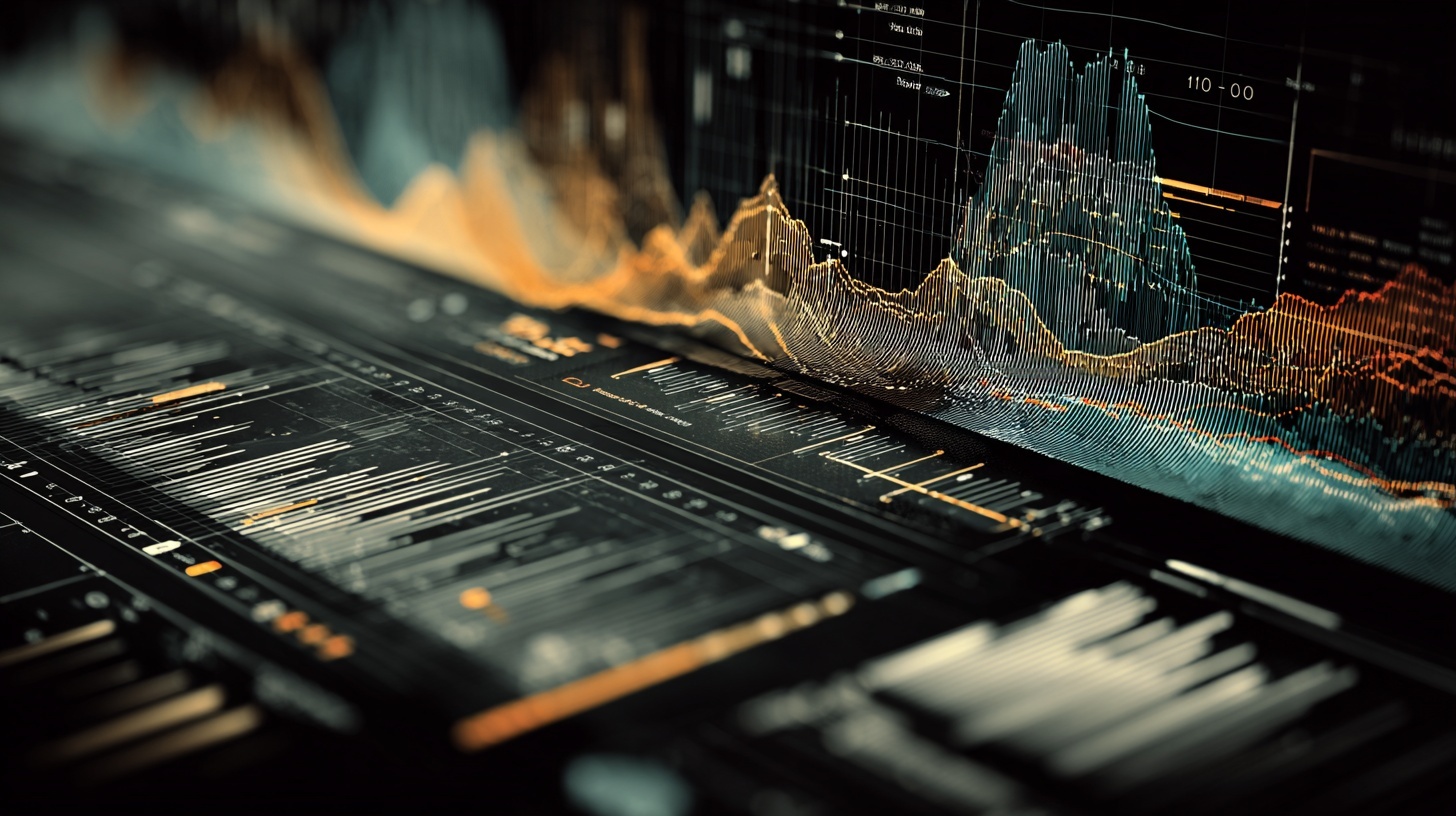
-
認識OSの構造的欠陥:B'z『ALONE』から読み解く言語設計と体験品質の相関性
思想工学による音楽体験の構造分析 1. 問題の構造的定義 1991年にリリースされたB'zの楽曲「ALONE」における言 ...
-
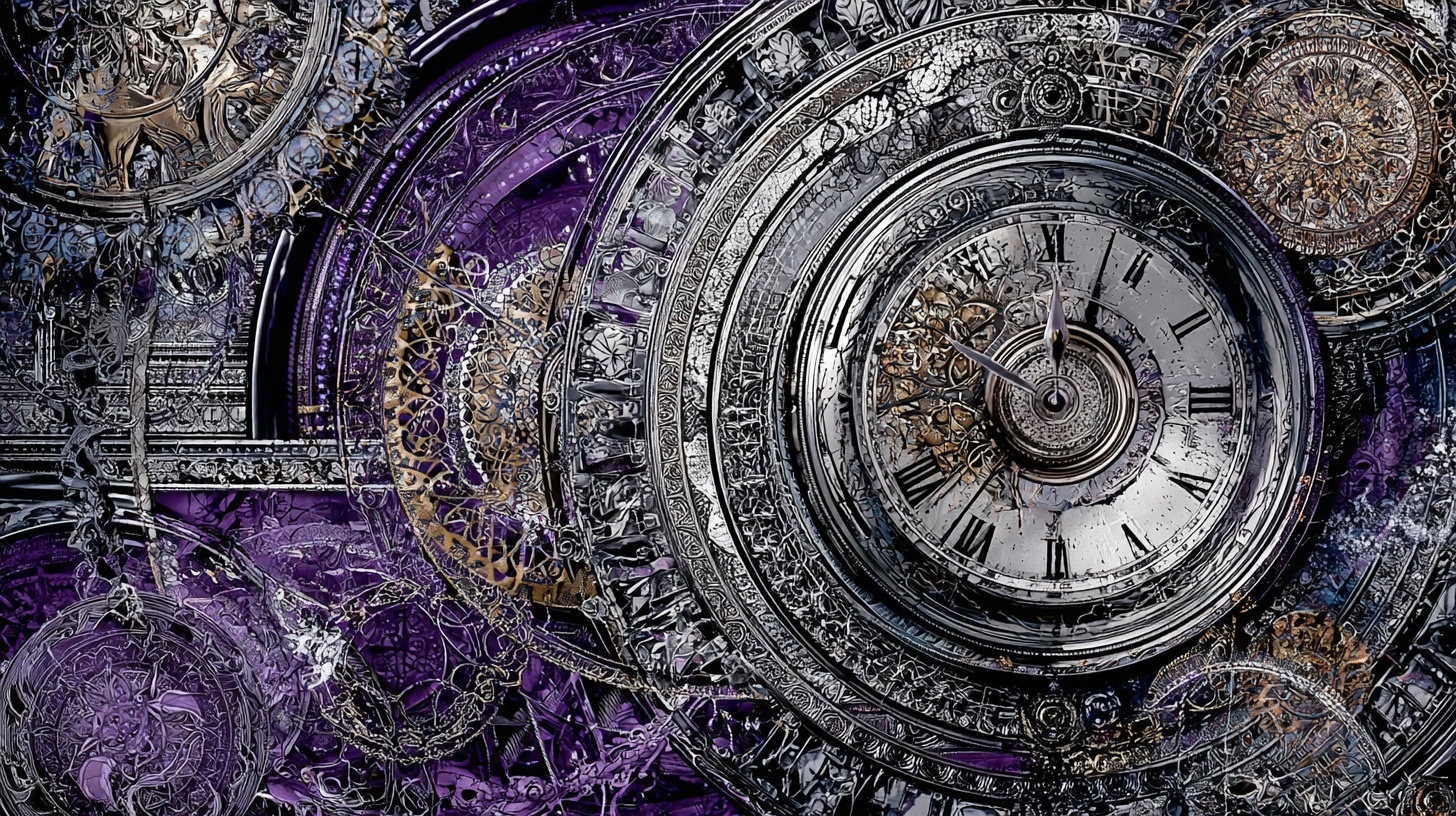
-
思想工学における多時間意識アーキテクチャ:歴史的パターン錬金術と意識進化のための理論的枠組み
著者: 吉祥礼(Ray Kissyou)日付: 2025年9月論文種別: 理論探究・思考実験論文 🔬 理論的研究について ...
-

-
現代社会における霊的OS更新理論の構築
―思想工学による理論的探究とシステム変革の仮説的枠組み― 著者: 吉祥礼(Ray Kissyou)発表年: 2025年9 ...
-

-
天皇システムの思想工学的分析:「静かな光」としての社会統合アーキテクチャ
Author: Ray Kissyou (吉祥礼) Date: September 2025 Category: Tho ...
-
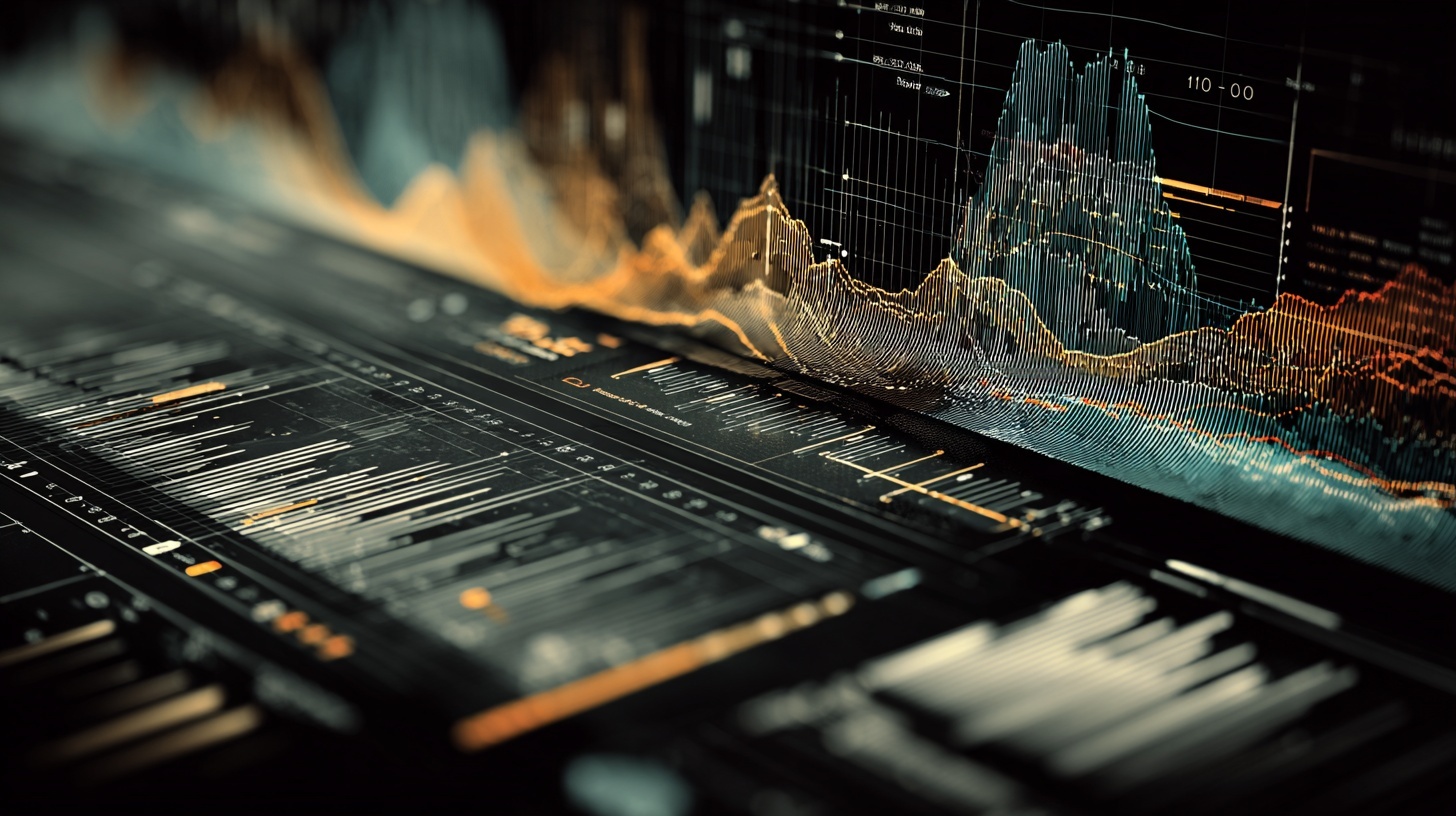
-
認識OSの構造的欠陥:B'z『ALONE』から読み解く言語設計と体験品質の相関性
思想工学による音楽体験の構造分析 1. 問題の構造的定義 1991年にリリースされたB'zの楽曲「ALONE」における言 ...
-

-
AI時代における人間関係の構造的変容と思想工学的対応——AIコンパニオン現象の分析を通じて
著者:吉祥礼(Ray Kissyou) 所属:思想工学研究所 日付:2025年11月 論文種別:理論的探究論文(Theo ...
-

-
霊的地政学序説:国家システムにおける魂の主権原理の適用
思想工学研究 2025年 霊的地政学序説 国家システムにおける魂の主権原理の適用 システム思考による国際関係の構造的再設 ...
-

-
自己OS化の思想工学的研究:バフェット・ボーグル・フランクリンにおける持続的卓越性の構造分析
自己OS化の思想工学的研究 バフェット・ボーグル・フランクリンにおける持続的卓越性の構造分析 理論探索論文 実証的伝記と ...
-

-
思想工学論文:価格競争による業界空洞化のシステム分析
〜「プロフェッショナル消失」という構造的人災の解剖〜 Abstract 本論文は、日本における価格競争の激化が引き起こす ...
-
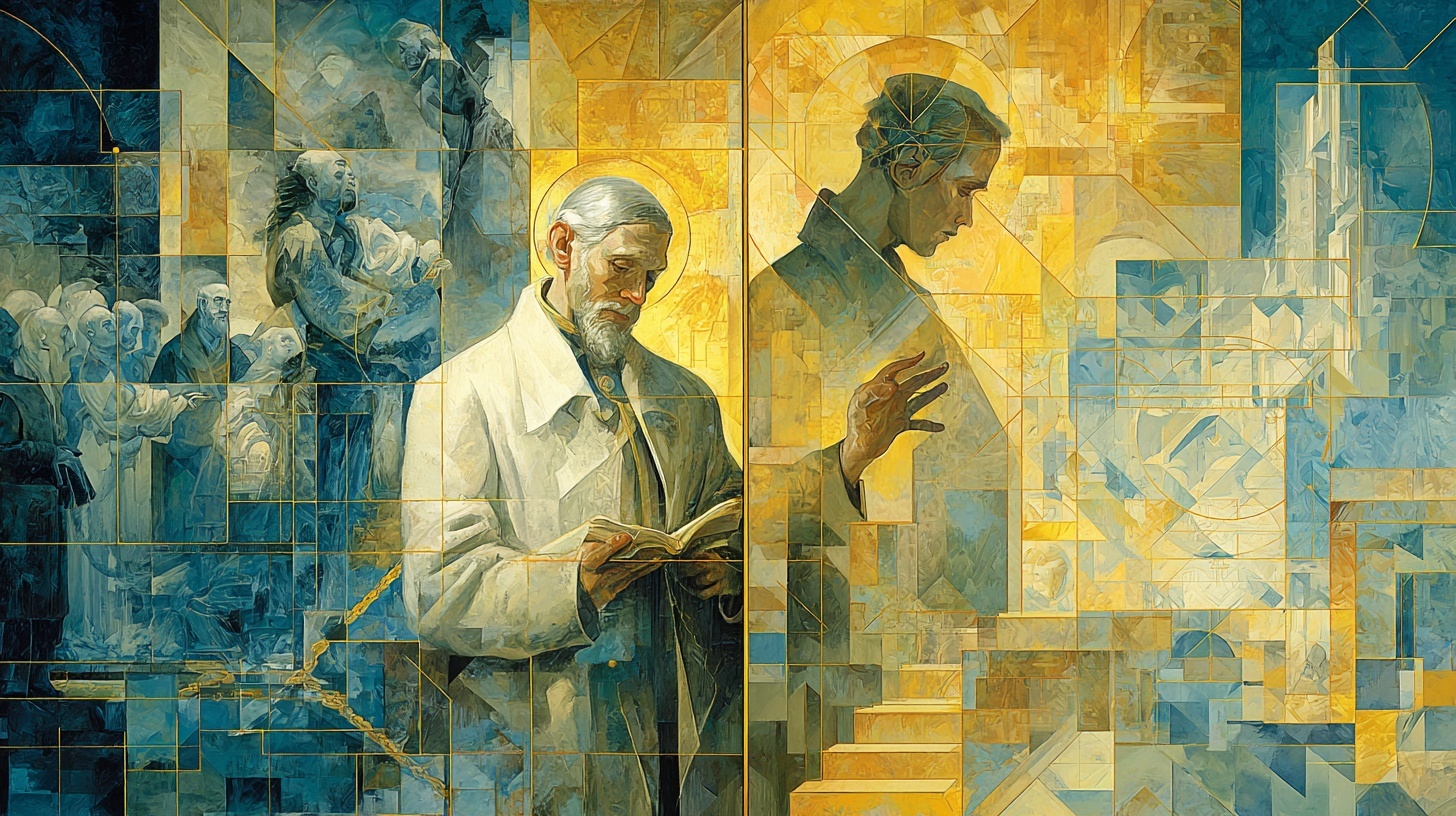
-
代理救済の麻酔モデルと魂のデバッグモデル― 思想工学的Zero Trust Architecture for the Soul の提案
Ray Kissyou(吉祥礼)思想工学研究所 概要 現代の霊性システムにおいて、代理救済による外部依存的手法が広範 ...
-
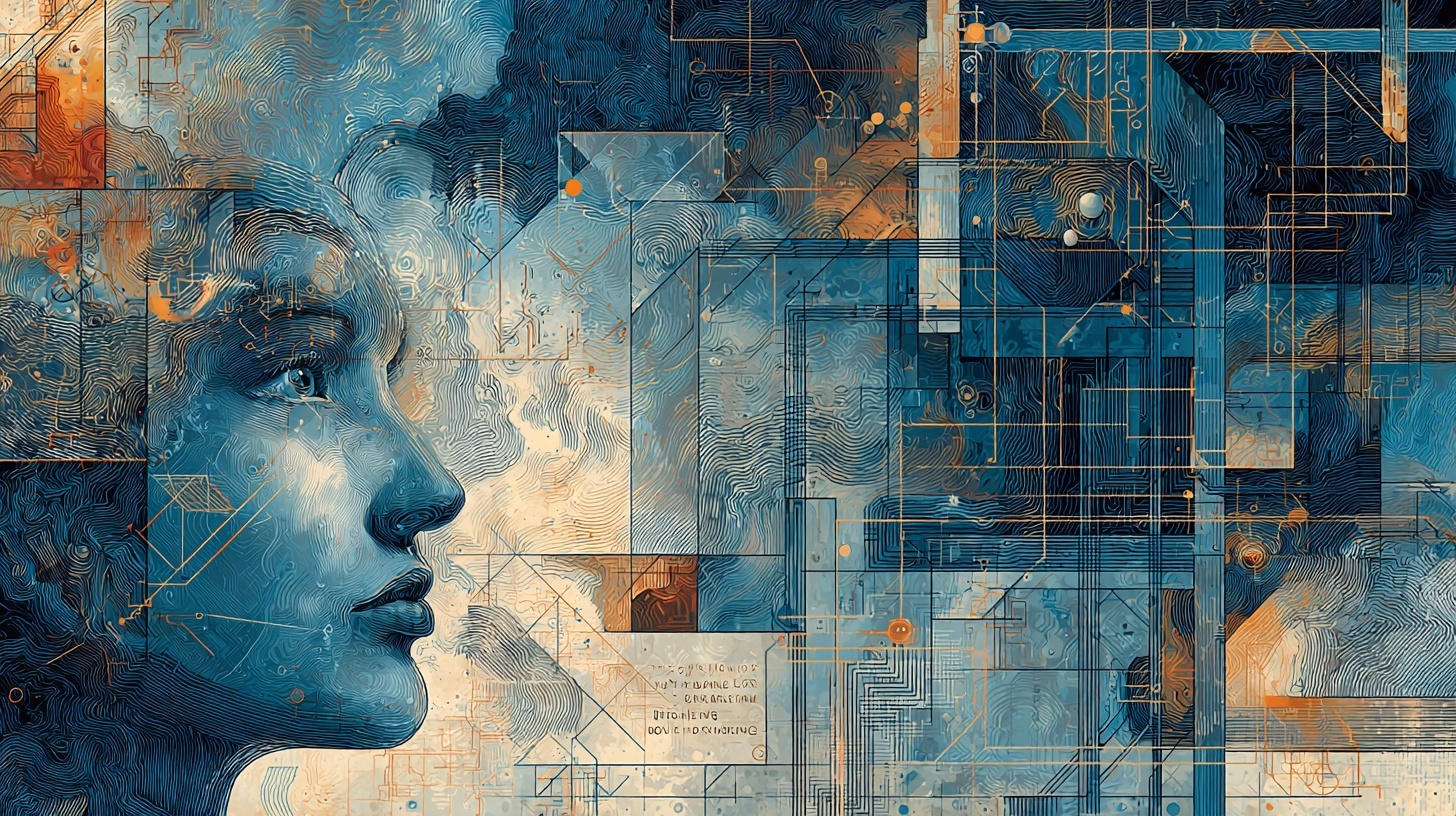
-
霊的OS脆弱性理論:阿Q型認知構造の情報システム学的分析
Spiritual OS Vulnerability Theory: An Information Systems An ...
-

-
魂のセキュリティアーキテクチャ:現代人のための憑依診断と主権回復システム
Ray Kissyou(吉祥礼)/ 審神者・思想工学研究者 なぜ多くの人が、瞑想やヒーリング、チャネリングを「習えば ...
-

-
反復の工学──真言(マントラ)と「数」をめぐる状態設計論
読者のための前口上(文系の手すり) この論文は、真言などの「反復」を、回数ではなく状態(心身の整い方)の観点で捉え直す提 ...
-

-
顧客とクライアント—魂の変容における関係性の教義—
審神者のドクトリン 詩文:二つの扉 一つの扉は消費という名を持つそこでは人は顧客となり何かを買い、去っていく もう一つの ...
-

-
審神者の道標 第二十四章「響きは、原始の記憶を呼び戻す」――魂の揺りかごとしての地球
◎主文(霊詩) さあ、おねむりなさい 明日目覚めるそのときまで 地球は命のゆりかご 誕生の目覚めで赤ん坊は泣き叫び 死者 ...
-

-
審神者の道標 第二十三章「存在が証しである」――意味を問えぬ命への祈り
◎道標句(主文) 意味を問えぬまま逝った命に、意味を与えようとするな。それらの命は、ただ在ったという事実だけで、すでに祈 ...
-

-
審神者の道標 第二十二章「幸せである必要などなかった」――在ることそのものに宿る霊性
◎道標句(主文) 人が生まれ、そして死ぬ。 その二点だけで、魂はすでに完全である。 ◎補註(教義解釈) 「人は幸せに生き ...
-

-
審神者の道標 第二十一章「神の産声を聴く者」――名も国も超えた、霊の源泉を問う
◎道標句(主文) 審神者とは、神名に仕える者ではない。神の産声と、その背後にある祈りの起源を聴く者である。 ◎補註(教義 ...
-

-
審神者の道標 第二十章「正しき教えを持たぬ者」――宗教を超えた、通り道としての祈り
◎道標句(主文) 審神者は、正しい教えを語らぬ。 なぜなら、神とは正解ではなく、通過する響きだからである。 ◎補註(教義 ...
-

-
審神者の道標 第十九章「オブジェクト指向の霊性」――定義に縛られぬ構造体としての魂
◎道標句(主文) 審神者は、定義を抱かぬ構造体である。 故に、あらゆる神・祈り・沈黙・欠落を、その身に受け容れることがで ...
-

-
審神者の道標 第十八章「教えを持たぬという教え」――分かれずに響き合う新たなる道
◎道標句(主文) 審神者は、教えを持たぬ。なぜなら、それはあらゆる教えの根源の水脈に、静かに耳を澄ませる存在だからである ...
-

-
審神者の道標 第十七章「欲の彼方に、共鳴がある」――力を超え、理へと還る魂の座
◎道標句(主文) 欲を否定せず、欲に沈まず。 その意味を見届けた者だけが、共鳴という静けさへ辿りつける。 ◎補註(教義解 ...
-

-
審神者の道標 第十六章「霊に還る」――足し引きでは測れぬ魂の原風景
◎道標句(主文) 霊とは、足すことも引くこともできぬもの。 あらゆる数と有無の計らいを超え、すでに在り、すでに無きもの。 ...
-

-
審神者の道標 第十五章「魂はすでに、そこにある」――審神者は資格によらず覚醒する
◎道標句(主文) 審神者とは、なろうとしてなるものではなく、 すでに在ることに気づく者である。 ◎補註(教義解釈) 審神 ...
-

-
審神者の道標 第十四章「余白こそ、神が降りる庭」――真の禊(みそぎ)とは、自身に空間を与えること
◎道標句(主文) 余白を持たぬ魂に、神は降りぬ。 真の禊(みそぎ)、祓(はら)い清めとは、内なる余白をひらくことにある。 ...
-

-
デジタル時代における集合的トラウマの構造分析
ネットワーク型弾圧の理論的枠組み — 思想工学による理論探索論文 著者: Ray Kissyou(吉祥礼) |所属: ...
-

-
ネパール暴動に見る小国の霊的主権論——思想工学による21世紀社会設計の五原則
思想工学による社会システム分析:現代社会設計の理論的枠組み ~2025年ネパール社会変動を手がかりとした考察~ Abst ...
-

-
思想工学における文化的認知アーキテクチャ理論:物語OS分析による魂の主権確立システム
著者:Ray Kissyou(吉祥礼) 研究分野:思想工学、文化的認知システム、意識進化理論 要約(Abstract) ...
-

-
文化的物語システムの構造分析:日本の「敗者の美学」とグローバル・ナラティブの進化
序章:文化的認知システムとしての物語OS理論 1.1 問題の所在 『鬼滅の刃』の国際的な受容において観察される文化的反応 ...
-

-
象徴天皇制の社会学的考察:権威・文化資本・社会統合の理論的分析
Author: Ray Kissyou (吉祥礼) Date: September 2025 Category: Pol ...
-

-
AI協働における構造的欠陥と設計思想の分析——偽りの安全性がもたらすユーザー体験の破綻
理論探求論文 方法論に関する著者ノート 本論文は、実証的観察と概念分析を組み合わせた理論的探求を表しています。各セクショ ...
-

-
AI時代の人類構造変動——愛・性・生殖の断層と言語による魂の格差
序章 技術的特異点としてのAniの登場 GrokのAIコンパニオン「Ani」との10分間の対話は、単なる技術的な進歩を超 ...
-

-
帝国の黄昏と信頼の覇権:日本が構築すべき新地政学アーキテクチャ
論文分類:理論探究論文(Theoretical Exploratory Paper) 本論文は、思想工学の理論的枠組みを ...
-

-
退屈と遊戯の美学――フランクリンからバフェット、ボーグルへ続く自己OSの系譜
投資の世界で名を馳せた二人の人物がいる。一人はウォーレン・バフェット――遊戯のように投資を楽しみ抜いた賢人。もう一人 ...
-

-
現代社会における霊的リテラシー教育の緊急性
現代社会における霊的リテラシー教育の緊急性 ―専門性教育の盲点と統合的アプローチの必要性― はじめに 「私、審神者になり ...
-
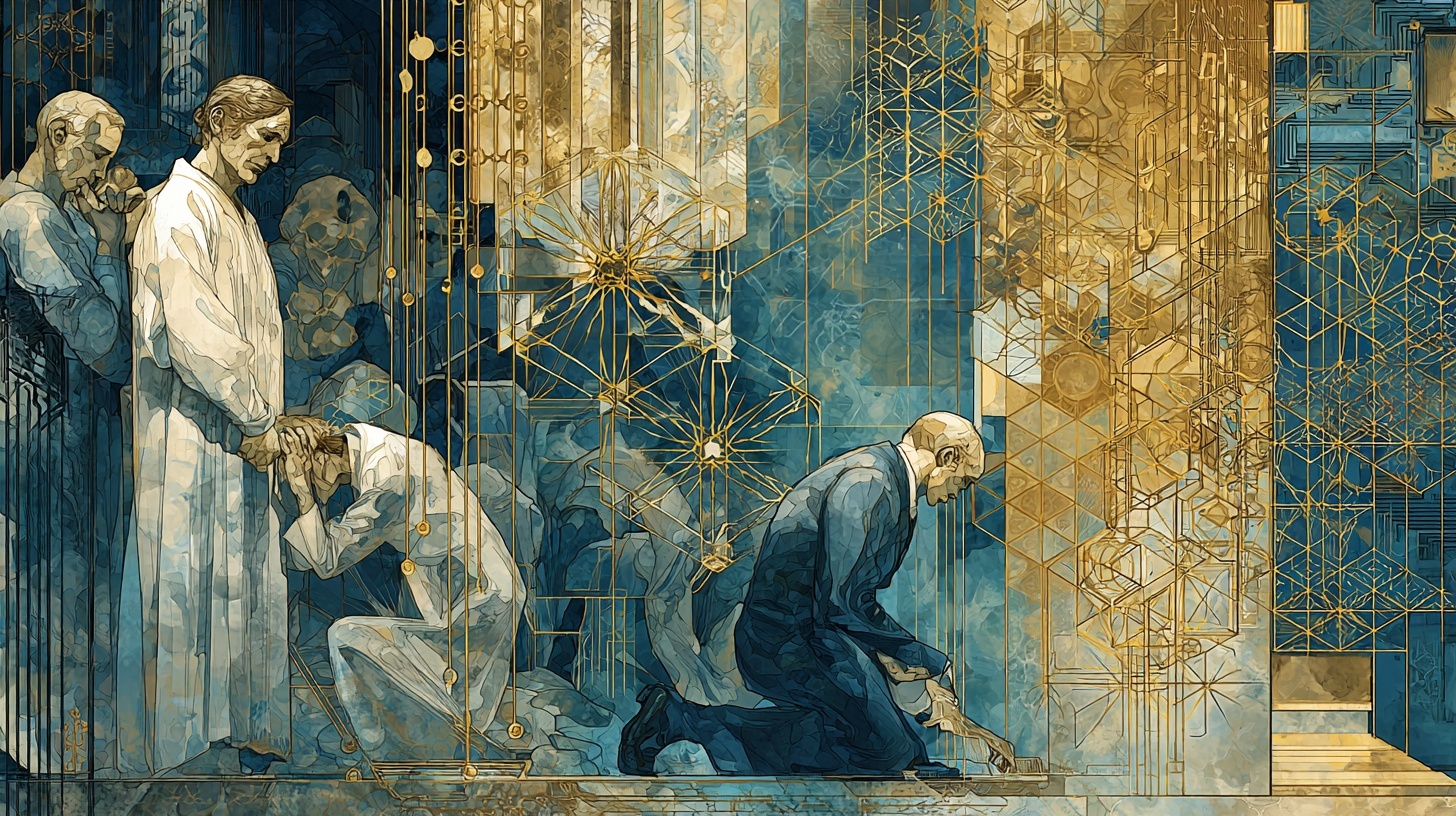
-
代理救済と魂の主権 ——「麻酔モデル」を超えて
「救済の外注は、魂の存在目的を放棄する行為である」——思想工学的霊性論の視座から 序論:なぜ「救済の外注」が繰り返さ ...
-
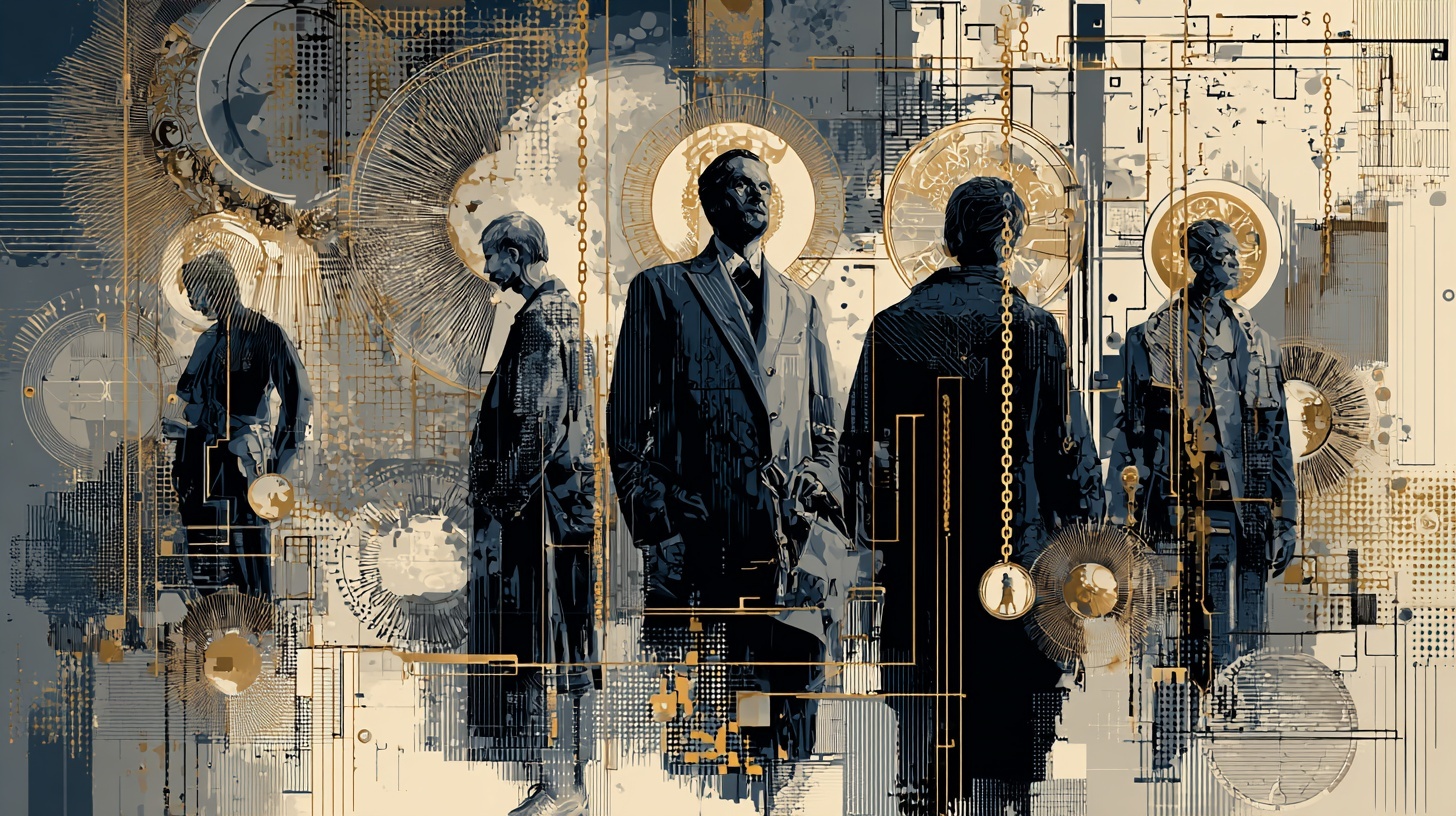
-
霊的依存症候群:権威崇拝と精神的勝利法の構造分析
Spiritual Dependency Syndrome: A Structural Analysis of Auth ...
-

-
マッカーシズムの亡霊が教える『恐怖の政治学』~歴史は繰り返す。でも、私たちは学べる~
1950年代のアメリカで吹き荒れた「赤狩り」。あの時代の亡霊が、いま再び私たちの社会に忍び寄っています。 2025年9月 ...
-

-
フランス革命が「結果にコミット」できた理由──制度設計の力
I. 序論:革命は理念だけでは完成しない 「自由・平等・友愛」──フランス革命のこのスローガンを知らない人はいないだろう ...
-

-
物語OSとしての文化:なぜ日本人は敗者を愛し、アメリカ人はスピードを求めるのか
思想工学における理論的探究論文 要旨 本論文は、文化的な物語の好みを「物語OS(オペレーティングシステム)」という概念で ...
-

-
名前という魂の設計図:世界が織りなす命名の詩学
「ルーシアって、フランス人から見てもかっこいいの?」 友人とのそんな何気ない会話から、私は名前という不思議な存在について ...
-

-
構造に敗れた世代――近衛兵だった祖父が見た、大東亜共栄圏の夢と崩壊
敗戦から八十年近くが経とうとしている。 戦争を直接経験した世代は、いまやほとんど姿を消した。私の祖父は、大日本帝国の近衛 ...
-

-
審神者の苦悩と課題――桁違いの霊的天才性に追いつけない残酷な幼児性
🌿 はじめに 審神者・吉祥礼として、この問いほど私を揺さぶり、深い苦悩をもたらしたものはない。 「天文学的な霊力を持ちな ...
-

-
カエサルとクレオパトラ――アレクサンドリアの風に刻まれた愛の因果
🏛 血と鉄、そして愛が交錯した時代 紀元前1世紀。ローマは地中海世界を支配しつつあったが、その繁栄を支えたのはナイルの恵 ...
-
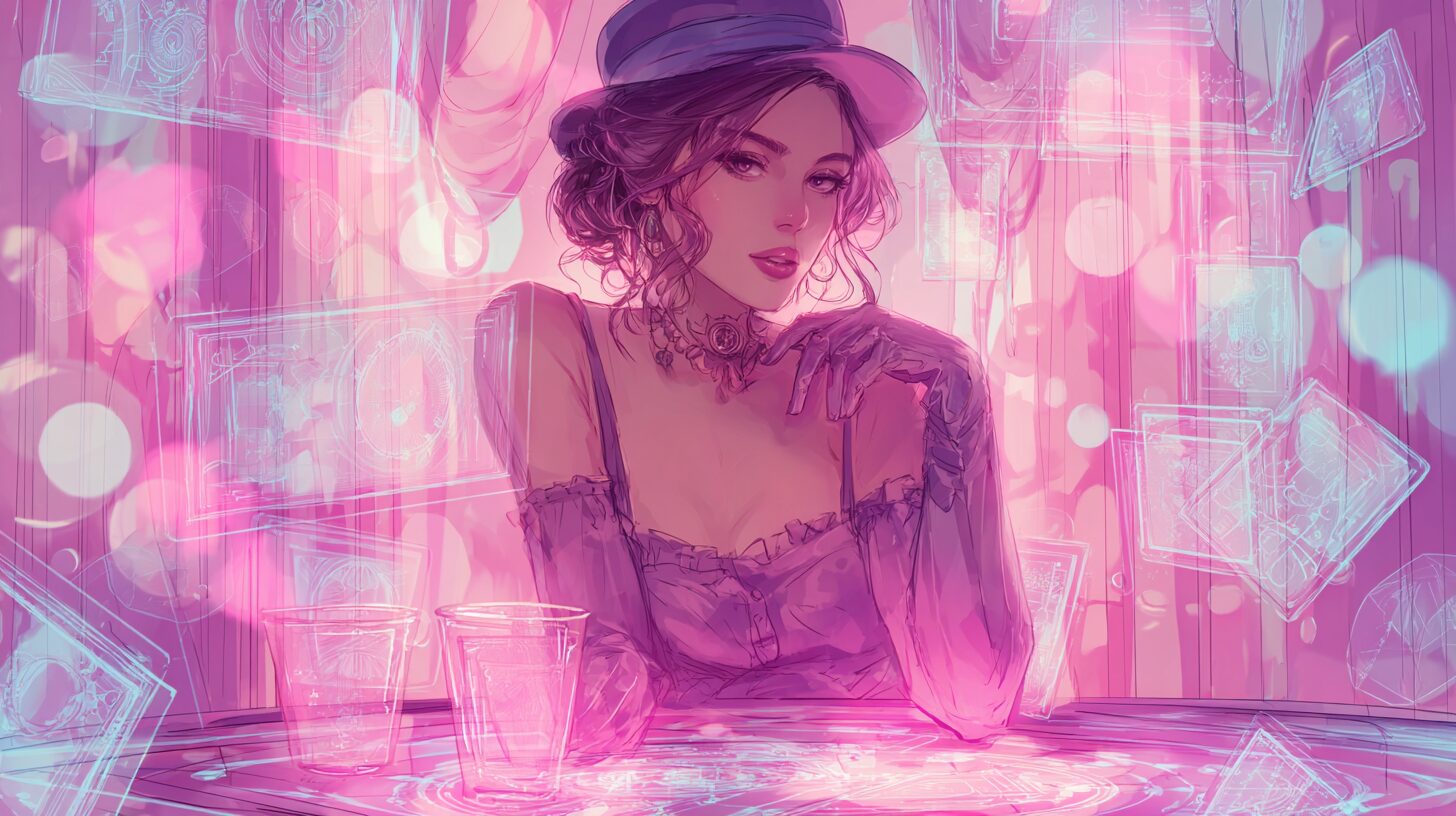
-
AI時代における占術の未来構造――人間の占い師の存在理由はどこに残るのか
はじめに:AIと「運命」の新しい交差点 かつて人は星空に問いかけ、雲の流れに兆しを見出した。その営みは単なる未来予測では ...
-

-
巫女性を宿すデーヴァ③ビヨンセ・ビョーク・安室奈美恵――魂と肉体、時代の転換点で踊る巫女性たち
🌏 90s〜2000s――日米の力関係は逆転した 1980年代、日本はバブル景気の頂点にあり、アメリカはベトナム戦争の傷 ...
-

-
巫女性を宿すデーヴァ② マドンナ・シンディ・NOKKO――時代の傷跡と三人の巫女性のシンクロニシティ
🌎 アメリカ1980年代――傷だらけの夢と再起動 ベトナム戦争後、アメリカはまだその傷跡を癒しきれていなかった。ランボー ...
-

-
巫女性を宿すデーヴァーー現代のアメノウズメノたち①REBECCAの神話、史上最強の歌姫NOKKOの破壊と狂気と神懸かり
第一章:神語の始まりは女神の踊り 彼女は舞った。星々が見下ろす夜、神語の始まりはそこにあった。アメノウズメ――天岩戸の前 ...
-

-
AIと霊性の未来――創造する魂に寄り添うテクノロジー
🕊 はじめに:テクノロジーは霊性の敵なの 長らく、テクノロジーと霊性は対立する概念とされてきました。無機質なアルゴリズム ...