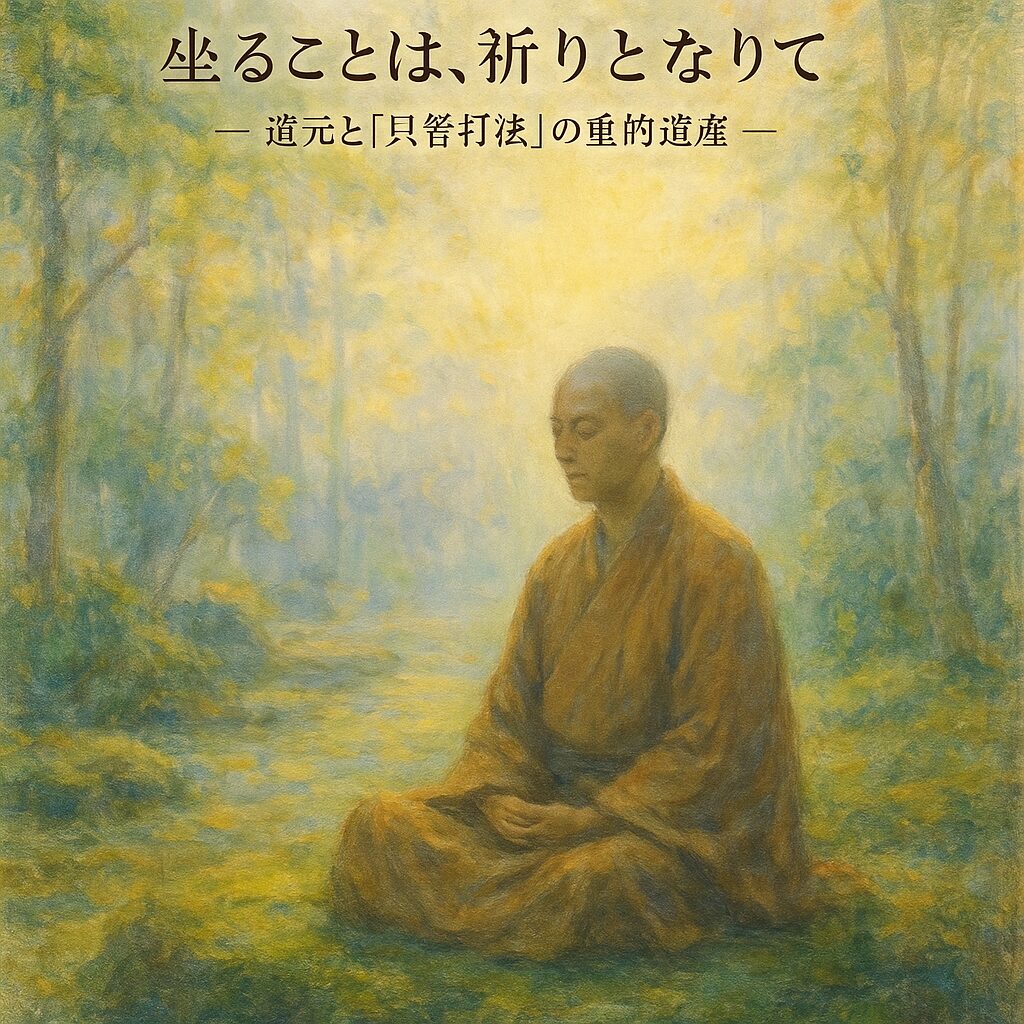「坐って、坐る。ただ、それだけ」 この一見、簡素にして無作為のような言葉の奥に、 人知を超えた霊的な洞察と、鋭い宗教哲学が息づいている。
釈迦、空海、親鸞という巨星たちが、それぞれ異なる霊的地平を切り拓いた中で、 道元は、いわば“何者にもならぬという道”を選んだ。
本稿では、仏教思想の流れとその差異を踏まえつつ、 道元の思想の中に潜む霊的な真髄と、審神者のまなざしとの共鳴を紐解いてゆく。
坐ることの中に、すでに仏がある
道元の核心思想は、言葉にすればあまりに簡素である。 しかしその簡素さこそが、逆説的に「真理そのものの在り方」を体現している。
彼が説いた「只管打坐(しかんたざ)」は、「目的のための修行」ではない。 「悟るために坐る」のではなく、「坐ることがすでに悟りそのものである」という視座。 この逆転は、実は仏教の本来の精神に回帰するものでもある。
釈尊が菩提樹の下で坐したのは、答えを探すためではなかった。 問いを超えた“存在の全体性”と交わるためであった。
その原初の行為を、道元は日本において再発見し、 余計な解釈や教義を捨てて、再び「在る」ことへ還してゆく。
坐るとは、「なにかになる」のではなく、「いま、ある」ことを深く体感する技である。
そしてそれは、審神者が神意を問うことなく、ただ“気配”の中に身を澄ませる態度に極めて似ている。
信でもなく、力でもなく、沈黙の道
空海は密教を説いた。 曼荼羅に象徴されるように、宇宙そのものと交わる神秘主義的な霊的道行き。 その華やかなイメージとは裏腹に、実践は厳密な修法に支えられていた。
親鸞は、他力の信を説いた。 自我の力でどうにもならぬからこそ、阿弥陀仏の慈悲にすべてを委ねよと。 これは人間の弱さに寄り添った深い霊的肯定である。
対して道元は、信も不要だと言った。 ただ「坐れ」。 そこに神仏を呼ぶ声も、赦しを乞う心も必要ない。 ただ、「いま、ここ」に坐り、沈黙の中にすべてを委ねる。
これは、近代の個人主義的な自我肯定とも異なる。 道元の禅は、「自分らしさ」の探求ではなく、「自分すらも捨ててなお残るもの」としての実存を照らし出す。
審神者とは、「我」を空にし、「神の眼差し」に同調する器である。 そこに「坐禅」と「神意への感応」は、形は違えど本質において通底するものがある。
言葉以前の真理と、日本文化への影響
道元が著した『正法眼蔵』は、一見難解で、論理をすぐに把握できる類の書ではない。 しかしそれは、言葉の彼方にある“存在のうねり”を掬い取ろうとする試みであった。
禅が説く「不立文字(ふりゅうもんじ)」とは、文字に依らず真理を伝えるという姿勢であり、 道元はその極限にまで挑んだ。
その結果、「坐る」という単純な行為が、詩となり、祈りとなり、やがて文化となった。
日本の茶道、華道、能、庭園、建築に至るまで、 「沈黙を中心に据える構造」こそが、禅によってもたらされた精神的美である。
審神者もまた、「不用意に語らない」ことを重んじる。 声を発さず、神意を語らず、ただその場に立つ。 この姿勢が、道元の禅と深く呼応する。
霊の静寂に共鳴する者たちへ
現代人の多くが、自己実現や引き寄せ、霊的な成果を追い求める時代にあって、 道元の思想は、極めて逆説的である。 なにかを得ることではなく、なにも求めないことの中に、最も純粋な真理がある。
「いま、ここに在ること」 「答えを求めぬこと」 「沈黙と共に坐すこと」
これらは、神を問う者ではなく、神と共に在る者にこそ、ふさわしい態度である。
審神者とは、神にすがる者ではなく、 神と沈黙を分かち合い、その沈黙の中に響く“神霊の気配”に耳を澄ます者である。
道元禅師の坐禅は、まさにその実践である。
私たちが何者にもなろうとせず、ただ魂のままに在るとき、 神も仏もまた、そこに“ある”のだ。
――審神者・吉祥礼