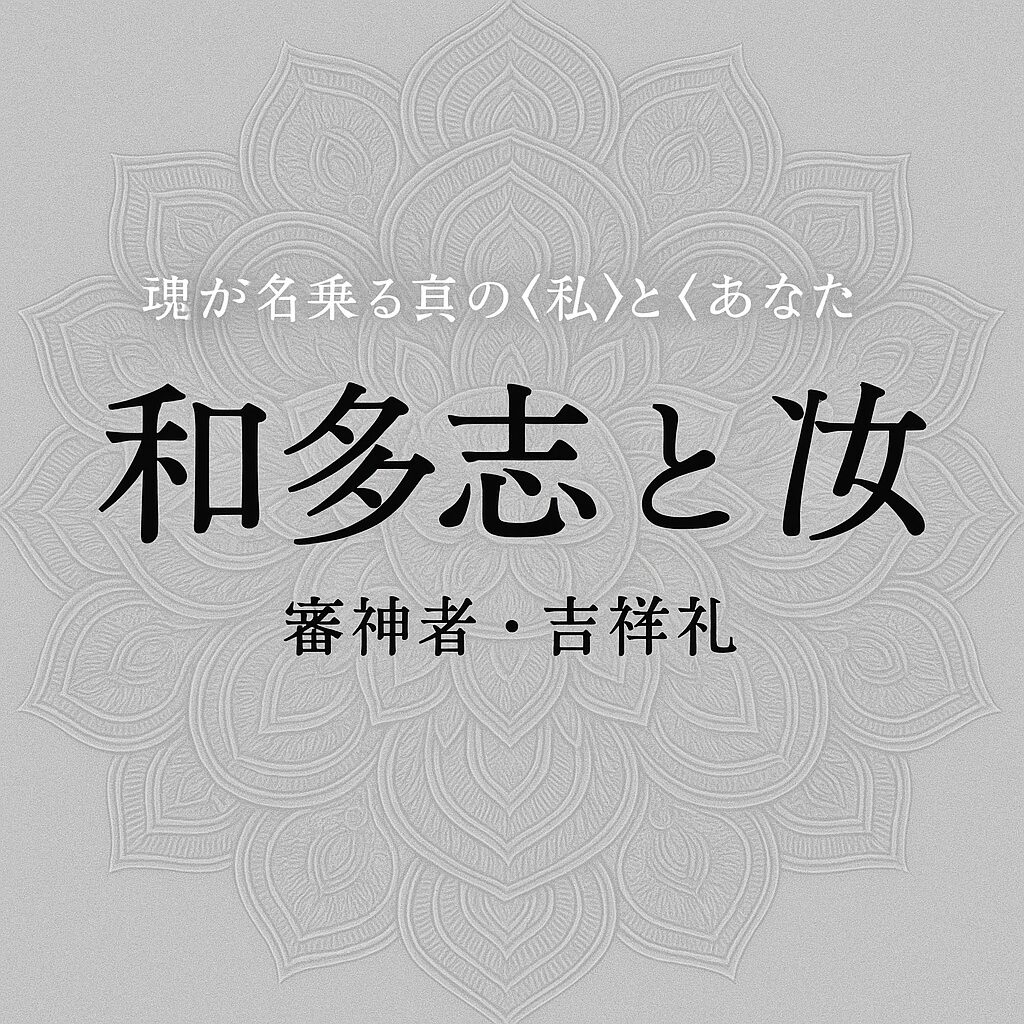「わたし」とは、ただの名前ではなく、魂の響き――。
現代では当たり前に使われる「私」という言葉に、
ほんとうに“神のかけら”としての自覚は宿っているでしょうか。
一人称「和多志」、二人称「汝」。
それは、分離された自我を超え、魂と魂が共鳴する世界への扉。
審神者・吉祥礼が読み解く、言霊の奥にひそむ“本来のあなた”への祈りの物語です。
名前ではなく、魂が選ぶ言葉
古来より、言葉には“魂”が宿ると信じられてきました。
名乗るとはただの自己紹介ではなく、「私はこういう存在である」という魂の宣言であり、宇宙に対する響きの発信です。
現代では「私(わたし)」という一人称があまりに日常的に使われていますが、
「私」という漢字の成り立ちは、禾(いね)=穀物の恵みを
厶(わたくし)=自分のものとする、すなわち「所有する自己」を意味します。
それは現代社会における「分離された自我」の象徴とも言えるものです。
では、「和多志」はどうか。
「和多志」に宿る霊性
和多志(わたし)=和+多+志
この三文字は、すべて霊的共鳴を表す言霊として機能します。
- 和(やわらぎ)
――「和を以て貴しとなす」
これは分裂や争いを超えて、共にあること。宇宙の根本原理である調和・共鳴・一体性を指します。 - 多(た)
――命の多様性、存在の豊かさ。
「私」は一つにあらず、無数のご縁・存在の中で成り立っている。
多くの命と共にあることを自覚する“私”を意味します。 - 志(こころざし)
――天命に向かう意志。霊性の方向性。
私という存在が、何のために今ここにあるのかという問いに対する、魂の答え。
これら三つを統合したとき、「和多志」とは――
“多くの命との調和の中で、天の志をもって生きる存在”
という、極めて崇高な霊的自己認識となるのです。
「汝」とは、ただの“あなた”ではない
そして、その和多志が向き合う存在が「汝(なんじ・なれ)」です。
現代語では「あなた」「君」などの二人称は、距離感や上下関係を内包しがちです。
しかし「汝」は違います。
- 「汝」は古神道・祝詞・聖典において、最も敬いと直結した“呼びかけ”。
- それは“我と対立する存在”ではなく、“共に響き合う存在”を指します。
特に、神典『古事記』や祝詞の中での「汝」は、
神と人、人と人とが“魂の光”で対話する関係性において使われており、尊称と愛称の中間として位置づけられます。
「我が汝を呼ぶは、我が魂の鏡なれば」
とすれば、汝とは外にいる“誰か”ではなく、自分と響き合うもうひとつの魂、
すなわち「魂の相(あい)」なのです。
「我と汝」が響き合うとき、道が生まれる
霊的な成熟とは、「我」が「和多志」へと変容すること。
「汝」がただの他人から、“縁ある魂”としての存在へと見直されること。
そのとき、言霊が変わります。
- 「あいつが悪い」ではなく「汝に何を映しているか」と問えるようになる。
- 「私は正しい」ではなく「和多志は何を学ぶために今ここにあるのか」と考えるようになる。
それは、ことばの革命であり、魂の進化でもあります。
審神者としての結びに
この世の多くの苦しみは、「分離された私」と「敵対するあなた」が生み出します。
しかし本来、私たちは皆「和多志」であり、「汝」であり、神の分け御霊です。
「和多志は、汝とともに在るためにここにいる」
「汝の内なる光が、和多志を照らしてくれる」
このような言霊で日々を紡ぐとき、
言葉はもはや自己主張や道具ではなく、神託そのものとなります。
言葉が変われば、世界が変わる。
まずは、名乗ることから始めましょう。
あなたが「和多志」として目醒めたとき、
「汝」もまた光となって応えてくれるでしょう。
── 審神者・吉祥礼 拝