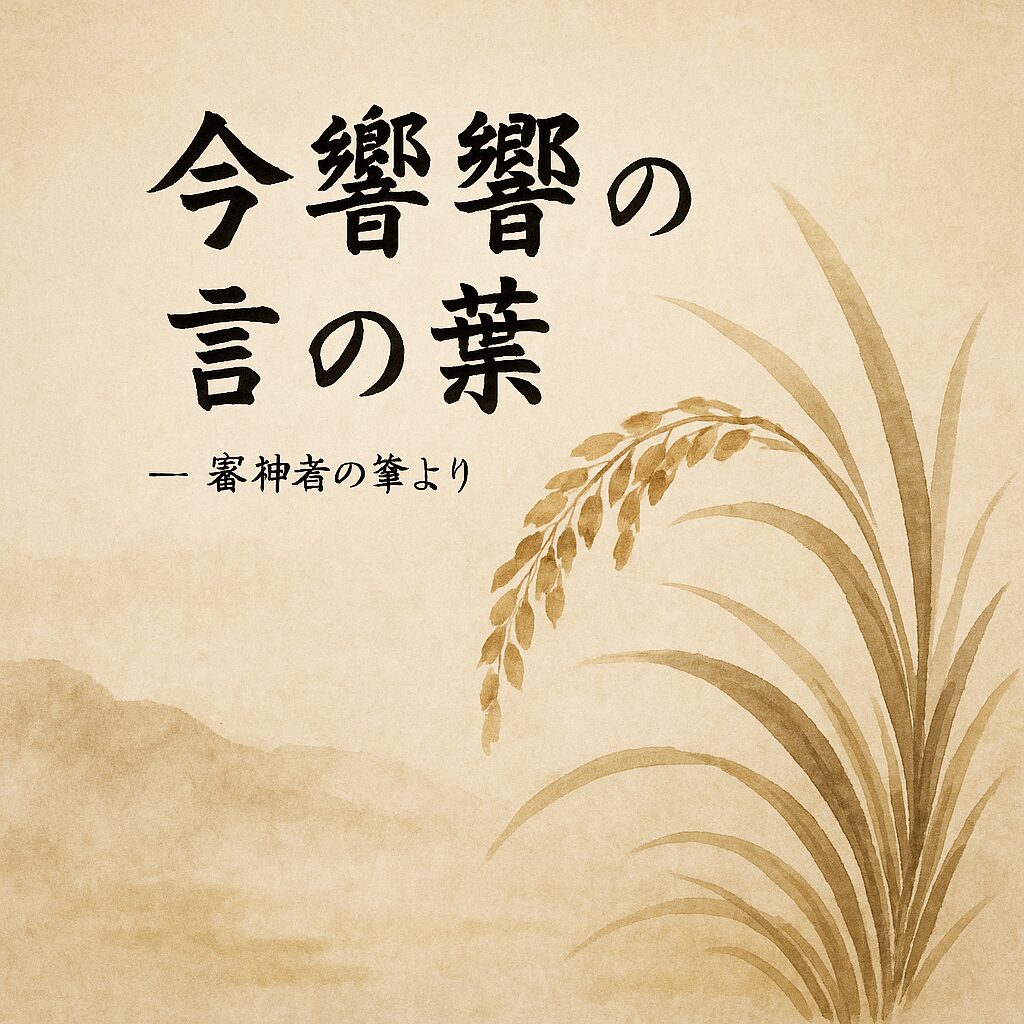日本という国は、稲の國である。
そして、その稲を育み、収穫し、感謝して食すという営みのなかに、
日本人の霊的な感性と倫理観、すなわち魂のかたちが深く息づいている。
稲は神々より授けられし神種(かむたね)であり、
高天原(たかまのはら)から地上に届けられた神聖なる霊糧とされている。
稲作は、単なる農業ではなく、神と人との間に結ばれた霊的な契約の表れであった。
田を耕し、苗を植え、太陽と水に感謝しながら実りを待つ。
そのすべての営みは、自然と共に生きるという日本人の魂の姿勢を育んできた。
自然を支配するのではなく、「神のはからいをお預かりする」意識。
それが日本の稲作に込められた祈りであり、謙虚さの源である。
米はただの食物ではない。
一粒一粒が命であり、言霊であり、祈りの結晶である。
おむすびを結ぶという所作にすら、「結び=産霊(むすひ)」の神性が込められている。
食べることは、神性を取り込み、魂を浄め、神とつながる行為だったのだ。
天地の恵みと人の手が重なってこそ、米は神の供物となる。
だからこそ「いただきます」「ごちそうさま」と唱えるその一言に、
八百万(やおよろず)の神々への感謝が含まれているのだ。
現代の私たちは、ついこの感性を忘れがちである。
だが、一膳のごはんの奥には、数千年にわたって続けられてきた命の継承と霊的感謝の習慣が宿っている。
いま一度、米を見つめなおしてみよう。
湯気立つ白飯の向こうに、
天照大神のあたたかなまなざしと、
先祖たちの祈りが見えてくるはずである。
今日の食卓に、一粒の米があること。
それは、日本人の魂が今も生きているという証そのものなのだ。
― 審神者の筆より