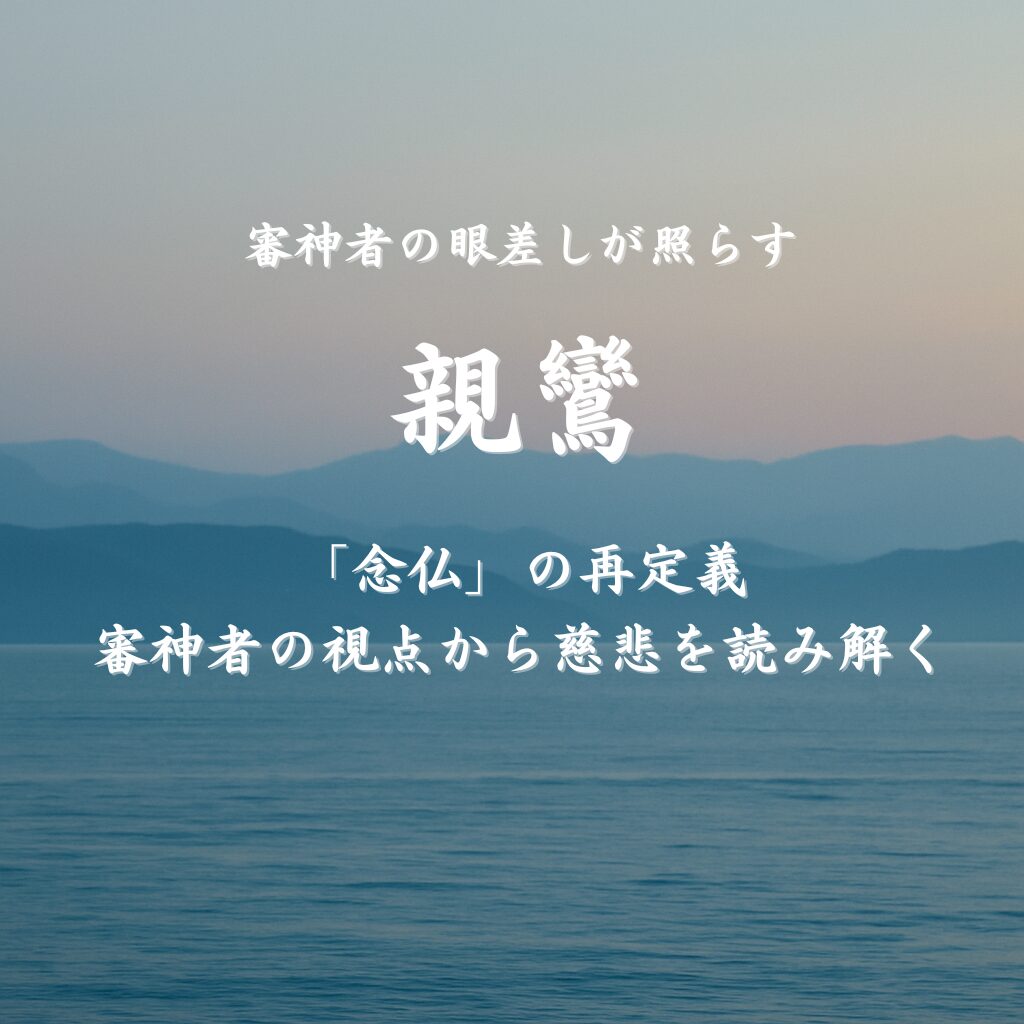「信じるだけで救われる」――そんな言葉に、どこか物足りなさを感じてきた人へ。
親鸞は語ります。「救いとは、すでに注がれている愛に気づくこと」。
審神者・吉祥礼の筆により、宗教の枠を超えた“祈りと霊性の真義”が、いま静かに照らされます。
空海に続く第二弾、今こそ日本人の魂に刻むべき「念仏の再定義」をお届けします。
――審神者・吉祥礼 記す
仏教を「民の祈り」へと降ろした革新者
親鸞は、空海とは別の意味で革命的な存在であった。空海が宇宙的次元の曼荼羅を地上に敷いたのに対し、親鸞は「庶民の心」へと仏を下ろし、“祈りの構造”を根底から変革した仏教の民衆化者であった。
浄土真宗の開祖でありながら、彼は自らを「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」と語り、信仰とは清らかな者のためではなく、迷いの中にある者のためにあるという大胆な逆説を提示した。
その思想は、日本の霊性に“恥を超えた赦し”を持ち込んだ。
念仏の革新――救済を自力から他力へ
親鸞が唱えた「南無阿弥陀仏」は、単なる宗教的呪文ではない。それは“我が身が既に救われている”ことを知るための響きであり、自力の修行ではなく、阿弥陀如来の誓願に身を委ねるという霊的降伏のことばであった。
「念仏は唱えども、念仏によって救うのは己にあらず」――この思想は、現代のスピリチュアルに蔓延する“自己実現のための祈り”とは本質的に異なる。
親鸞は、念仏を通して自我の執着を手放し、“己を救える存在ではない”と自覚することの中にこそ、真の光があると説いた。
「あなたは仏である」という衝撃的な内在論
親鸞の教えは、どこかキリスト教における「神の似姿としての人間」の概念に通ずる。
つまり、「阿弥陀の光は等しくすべての者に注がれている」という教えは、「神はすべての人に愛を注いでいる」というキリストの教えと、霊的構造が酷似しているのである。
そして親鸞は、そこから一歩進めてこう説いた――
"念仏をとなえる我とは、すでに仏の光のなかにある身である"
この思想は、人間は仏になるのではなく、すでに仏の中に包まれている存在であるという、内在的信仰への転換をもたらした。
先祖供養と霊的自律
日本人の霊性に深く結びついた「先祖供養」の慣習についても、親鸞は異端であった。
「亡き人を成仏させるのは、我にあらず。ただ阿弥陀の光に委ねるのみ」
この一文には、霊能や供養ビジネスに頼らずとも、すでに先祖は阿弥陀の慈悲に包まれているという、明快かつ揺るぎない信仰がある。
親鸞は、祈祷師に頼らずとも、「信じることで祈りが完成する」という霊的自律の姿勢を明示した。
それは、審神者の視座から見ても非常に重要な思想であり、今の時代に再評価されるべき“祈りの成熟”と言える。
親鸞の教えは“愛される覚悟”の教え
親鸞の教えは、つまるところ「愛されることを赦す勇気」に満ちている。
阿弥陀如来の光とは、条件のない、無限の慈悲である。 それを受け入れるとは、自らの無力を受け入れることであり、他者にもそれを赦すという連鎖の慈愛を生むことなのだ。
審神者の立場から言えば、親鸞は「祈りにおける自己神化の危険」を早々に見抜き、 そのかわりに“すでに愛されていること”を信じるという、受容の霊性をこの国にもたらした。
いま、誰かを救いたいと願う者はまず――
「すでに救われている私」を赦し、 「その私が誰かを包むこと」を信じるべきである。
それこそが、親鸞が遺した“沈黙の救済”のまなざしなのだ。